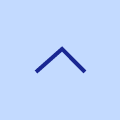高いお金を出したのに、こんなはずではなかった? ERP導入によくある失敗例と成功への対策
近年、経営を支えるとシステムしてERPを導入している企業が増えています。しかし、ERPは万能ではありません。「生産性向上」や「業務効率化」を期待して導入したにもかかわらず、かえって業務が非効率になるケースも少なくありません。多額の費用を投資するERP導入を成功させるために、よくある失敗例と、そうならないための対策について解説していきます。
ERP導入の落とし穴、よくある失敗例
ERPの導入に失敗するケースの原因はさまざまです。その中からよくあるものを紹介しましょう。
●目的が不明確
多くの企業が「生産性向上」や「業務効率化」を目的としていますが、具体的な目的が設定されていないと失敗します。
よくある失敗例:
他社事例の盲目的な模倣・・・「同業他社が成功しているから」という理由だけでは不十分です。自社の状況に合致するかを精査する必要があります。
高価格帯製品への過信・・・高価な製品だからといって、必ずしも自社の業務に最適とは限りません。機能とコストパフォーマンスを慎重に検討すべきです。
導入優先、カスタマイズ後回し・・・後からカスタマイズすると費用と時間が膨大になります。導入前に綿密な計画が必要です。
対策:
- 自社の課題を明確化し、ERPで解決できるかを検証する。
- 具体的な目標数値(例:受注処理時間20%短縮)を設定する。
- 業務フローの見直し、データベース設計などの準備を十分に行う。
●経営トップが積極的にプロジェクトへ関与しない
ERPの導入は業務プロセスの変更など、多くの社員に影響が及びます。経営トップが関与せず、プロジェクトを導入チームへ任せきりにした結果、部門間の対立や導入後の活用不足といった問題が発生します。
よくある失敗例:
目的・ビジョンの欠如・・・ERP導入についてはっきりした方針が決まっていないと、プロジェクトは迷走しがちです。経営トップは確固たる目的とビジョンを持ち、それを各社員に伝えるべきです。
部門間の対立・・・プロジェクトチームや現場にはそれぞれの立場からの主張や要望がありますので、これを放置すれば社内の対立を招きかねません。間を取り持つ調整役が必要です。
対策:
経営トップがプロジェクトを主導し、目的・ビジョンを全社に共有する。
部門間の調整役となるプロジェクトリーダーを配置する。
定期的な進捗報告と課題共有を行う。
●プロジェクトにチェック体制が欠けている
プロジェクトを進めていく過程においては、導入の目的と期待できる効果にズレが生じてしまうことがしばしばあります。そして、そのままプロジェクトが進行してしまうと、後から軌道を修正する際に多くの時間やコストを費やす羽目になります。これは、プロジェクトに適切なチェック体制が欠けていることが原因です。
よくある失敗例:
本来の目的からの逸脱・・・現場から出るさまざまな要望に応えるようと調整を行った結果、期待した効果が出ないことがあります。方針が導入の本来の目的からずれないよう、定期的なチェックが必要です。
対策:
- 定期的な進捗チェックと軌道修正のための体制を構築する。
- 導入後も効果測定を行い、必要に応じて改善を行う。
●ベンダーに丸投げしてしまう
ベンダーはERPの専門家ではありますが、貴社業務の専門家ではありません。丸投げせず、自社主導でプロジェクトを進めることが重要です。
よくある失敗例:
業務との不一致・・・プロジェクトをベンダーに丸投げしてしまうと、自社の業務プロセスに合わないシステムができあがってしまうことがあります。業務に最適なシステムを構築するためにも、プロジェクトには積極的に参画すべきです。
対策:
- ベンダー選定時に、同業種での導入実績や、課題への対応力、信頼できるか、などを確認する。
- 業務プロセスを詳細に共有し、ベンダーと綿密な連携を行う。
失敗しない導入プロジェクトの進め方
さまざまな失敗例を見てきましたが、このようなトラブルを招かないため、綿密な計画と準備が必要です。
計画段階:
・関係部署を巻き込んだプロジェクトチームを編成する。
・具体的な目標とロードマップを作成する。
・経営陣がプロジェクトを主導する。
導入段階:
・ERPの標準機能を最大限活用し、業務プロセスを最適化する。
・部門間の利害調整を行い、協力体制を構築する。
・ベンダーと緊密に連携し、課題を迅速に解決する。
ERP導入の際に技術面で注意すべきこと
ERPの導入においては、多くの企業がERPパッケージを選択しています。ERPパッケージでは、生産計画/所要量計算/需要予測/販売管理/在庫管理/原価管理など、標準的な業務に合わせて必要な機能が網羅されています。そのため、スクラッチでの開発に比べて短期間で導入でき、初期費用も抑えられるというメリットがあります。
ただし、製品によっては、自社の業務をカバーしきれないケースがあるかもしれません。そのため、なるべく幅広い業務をカバーしている統合型ERPパッケージを選択すると良いでしょう。統合型ERPを選択することで各業務のデータも統合管理されるので、データの重複入力や手集計がなくなるほか、スムーズなシステム間データ連携が実現します。
また、ERPの導入後、取引データなどの増加に伴って処理が遅くなり、業務自体に影響を及ぼしてしまうこともあります。こうした問題への対処としては、インメモリ型データベースの採用により、従来のデータベースと比べて圧倒的な高速処理を可能にする「SAP® Business ByDesign®」の選択をお薦めします。
ERP導入を成功に導くステップ
ここまでお話ししてきたポイントをもとに、ERP導入を成功に導くステップを以下でご紹介します。
①目的の明確化
世の中には多くのERP製品が存在しますが、それぞれ機能や特徴が異なります。ただ有名だからといった理由で製品を選んでしまうと、業務に合ってない、使い勝手が悪いなどと現場の反感を買い、失敗する原因になりかねません。よって、導入前に各部門の業務フロー、改善すべき課題などを明確にし、導入によって何を実現したいのかを明確化することが大切です。そうすることで、自社が必要とするものも明確になり、製品のベストな選択につながります。これはベンダーの選定についても同様で、導入の目的と業務の内容についてよく理解してくれるところをパートナーに選ぶべきです。
②プロジェクトチームに最適なメンバーを選ぶ
ERPの導入では、プロジェクトチームが計画と編成を行い、定期的なミーティングで進捗状況を確認しつつ、問題に対処していくのが基本です。プロジェクトチームと各部門との調整をスムーズに行うためにも、経営トップがプロジェクトオーナーを務めることが望ましいでしょう。プロジェクトリーダーには各部門の意見や要望を調整できる者を指名するとともに、導入で影響を受ける各部門の責任者を参加させることも欠かせません。
③インフラを整備する
リソース不足などの理由から自社(オンプレミス)での運用が難しいケースも考えられます。こうしたときにお勧めしたいのがクラウド型ERPです。クラウド型はオンプレミスよりも短納期・低コストで導入でき、メンテナンスも不要なことから、中堅・中小企業を中心に導入が進んでいます。
④業務改革の実施
ERPの導入は対象範囲が全社に及び、業務プロセスの変更など現場にも大きく影響を及ぼします。一方で、現場の要望を限りなく取り入れようとするとカスタマイズが必要になり、かかる時間やコストが膨大なものになってしまいます。そこで、ERPの導入に合わせて従来の業務を見直し、ERPの標準機能に寄せ、業務プロセスを最適化するようにします。
⑤社内教育を行う
ERPの導入後、効率的に活用するためには、運用ルールの策定と社内教育が不可欠です。せっかくERPを導入しても、現場が使いこなせなければ負担だけが増えてしまうことになりかねません。そうした事態を回避するためにも、プロジェクトチームのメンバーはもちろん、各部門のリーダーが中心となって、ERPの利用を社内にしっかり浸透させていく取り組みが必要です。
⑥導入後の運用を整備しておく
導入後のトラブル発生に備えて、迅速な対応ができるよう運用体制をしっかり整備しておく必要があります。また、導入の効果測定を定期的に実施することで、本来の目標や構想とのズレを修正したり、より効果を高めるための方策を検討するなどの見直しを行います。
まとめ
ERPの導入を成功させるには、目的を明確にした上で、企業の方針を決める立場にある経営トップが責任をもってプロジェクトに関わり、導入をリードしていくことが大切です。導入後も、目的に合った効果が出ているのかしっかりチェックしていく必要がありますので、この際も経営トップが客観的な視点でモニタリングし、改善が必要です。